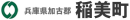明石市・神戸市・加古郡の新築戸建,中古戸建,中古マンション,土地,注文住宅なら神戸カーペンターズ
豊富な物件情報からお客様の予算にあった物件をご紹介いたします。
中古住宅、中古マンション購入後のリフォーム、リノベーションもお任せください!
弊社はリフォーム部も設置しておりますので、物件探しと並行してリフォーム相談も承ります。
自然素材を使用したこだわり注文建築、ローコスト注文住宅に特化した注文建築と2つの注文建築も承ります。
迅速、丁寧をモットーにお客様のお力になります。
お気軽に下記フリーダイヤルにてお電話ください。- TEL : 0800-816-9669
9:00~19:00
- 明石で家を探すなら神戸カーペンターズ
- 購入前のお役立ち情報の記事一覧
- 住宅ローン控除を学ぼう!
- 明石市エリアガイド
- 購入前のお役立ち情報
- ご成約キャンペーン!
- お客様の声
- 空き家管理サポート
- 資料請求、お問合わせは
- ㈱神戸カーペンターズ
- 兵庫県明石市大久保町大窪331-1
- Tel.0800-812-9201 Fax.078-934-9505
- http://kobe-carpenters.jp/